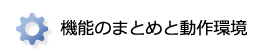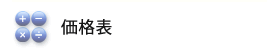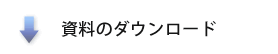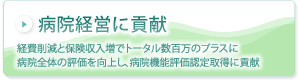東京女子医科大学病院
薬剤部と診療部門とを結ぶ医薬品情報統合システム 医療の質を相乗的に高めるチームプレーの礎に
医師から薬剤部への問い合わせは、『医薬品の添付文書を見れば解決する疑問』と『添付文書の情報では判然とせず、薬剤師に相談を要する疑問』が混在するのが一般的だ。しかし、東京女子医科大学病院では、医師が直接、電子カルテおよび基幹システムから、PDF化された医薬品添付文書を呼び出し、薬剤鑑別のほか、薬価や後発品に関わる情報などを入手できる仕組みを整えたため、問い合わせにおける前者の比重は大幅に減った。その分、薬剤部では、より臨床に近い業務に集中できるようになった。
添付文書の内容をデスクトップ上に表示 禁忌や副作用を医師がすぐ把握可能に
東京女子医科大学病院では、医薬品情報統合システムを2006年8月に導入。医薬品に添付される文書は、医師の手元のパソコンの画面から一覧可能になった。つまり、『添付文書を見れば解決する疑問』は、医師がその場で解消できるようになった。
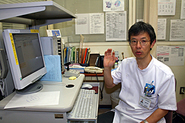 「いちばん知りたいのが、禁忌に関する情報」という麻酔科医の加藤隆文氏
「いちばん知りたいのが、禁忌に関する情報」という麻酔科医の加藤隆文氏
「1日に平均して30人分のカルテに目を通す」という麻酔科医の加藤隆文氏。そのうち約4分の1に相当するカルテに関する薬剤について、デスクトップPC の画面から添付文書の画像ファイルを閲覧する。患者に処方する薬の用法・用量や、注意事項を確認するためだ。普段よく処方している薬でも、副作用などが新たに追加・変更されていないか入念に確かめる。
「いちばん知りたいのが、禁忌に関する情報。大学病院では、複数の科で治療を受けている患者も多い。十種類以上、服薬されているケースもある。重大な相互作用がないか、特に注意を払って確認している」(加藤氏)。
2003 年に建設された総合外来センターでは、電子媒体による診療情報の伝達網が整備され、各診療科からは患者の電子カルテ情報を参照することが可能になった。同院で処方された薬歴についても、各科の医師などが入力しているため、どの科からも一覧できる。外来だけでなく、入院病棟のカルテについても電子化を段階的に進めている。現在は6割程度までが電子化され、外来と病棟が一体化した機能的総合医療施設へと着実に変貌を遂げつつある。
 JUS D.I.のインターフェース。左側に錠剤の写真が表示される
JUS D.I.のインターフェース。左側に錠剤の写真が表示される
「各医師の担当科以外の処方薬について、改訂される情報も含めて、すべて把握するのは現実的に難しい。ずいぶん昔であれば、医師の手元に実物があって、直接窓口へ渡すこともあった。しかし、処方を書くだけになってしまった今では『いつも処方されている、あの錠剤を飲むと、お腹が緩くなるんだよね』と患者に言われても、ピンとこないときもある」と加藤氏は打ち明ける。しかし「医薬品情報統合システムを導入してからは、患者のいう薬の特徴から候補を出し、画面を見ながら剤型を一緒に確かめることができるようになった。薬剤名が明らかになれば、PDF形式で電子保存された添付文書をその場で呼び出し、禁忌などを調べることができる。以前は、医薬品ハンドブックなどをめくっていたが、詳しい剤型まではさすがに分からない。その時に比べるとスピーディになっている」と加藤氏は付け加える。
医薬品情報統合システムの導入前は、添付文書の内容を知るために、薬剤部に問い合わせることが当たり前だった。だが時に、薬剤部も調査に時間を要することもある。頻繁なやりとりや、折り返し待ちは、患者を待たせる一因ともなった。医師も薬剤部に頻繁に連絡を取ることに、気兼ねする気持ちもあったという。
それが、医薬品情報統合システムの導入によって一変した。
「この薬とあの薬を併用していいのか、相互作用は何か、まずは一人ひとりの電子カルテの処方歴を見て、薬剤名からPDF化された添付文書を呼び出す。禁忌などに関する重要な情報が得られれば、処方を変える。わざわざ薬剤部に問い合わせをしなくてよいので、その分短時間で結論を出せるようになった。仮に、添付文書を見ても解決できない気がかりな点があれば、薬剤部に尋ねるが、その時点で、こちらも薬に関する予備知識を得ているので、従前に比べればやりとりは円滑になっている」(加藤氏)。
医師・薬剤師が添付文書の情報を共有するメリットは、対応負荷の軽減という形で双方に現れている。
資料作成などの効率化により、薬剤部も臨床業務の支援に注力
医薬品情報統合システムにおけるパッケージの選定では、4社の製品を比較検討。日本ユースウェアシステムの「JUS D.I.」を採用した。JUS D.I.は最新の医薬品情報データベースを提供。オンライン/オフライン経由で日々情報を更新できるほか、持参薬の鑑別レポート作成機能や、後発品を容易に検索することができるので、JUS D.I.の機能を利用して、後発品採用時のレセプト電子化加算(レ点チェックによる加算)を容易に行える、といった各種機能の充実を評価した。
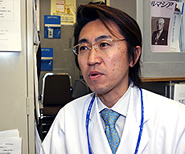 薬剤部副部長の木村利美氏は「情報が常にアップデートされている点がきわめて重要」という
薬剤部副部長の木村利美氏は「情報が常にアップデートされている点がきわめて重要」という
同院では、最新の添付文書などのデータは、オンラインで毎日定時に入手している。セキュリティを確保するため、その都度データにウイルスチェックをかけ、安全性が確認されたクリーンなものだけを、イントラネット内のファイルサーバーにダウンロードしている。
薬剤部副部長の木村利美氏は、「情報が常にアップデートされている点がきわめて重要。製薬会社の担当者やホームページからも改訂情報は入ってくるが、漏れやタイムラグの発生がどうしても避けられない」と述べる。
同院では、医師数は732人(2007年1月現在:女子医大のWebサイトより)。それに対して薬剤師は現在73名。薬剤部は、病院内の診療部門と密な連携をとりながら、入院患者志向の業務に力を入れているところだ。
「化学療法の充実や抗がん剤の混合調製への取り組みなど、薬剤部も臨床に近い立場で様々な施策を展開している」と木村氏は説明する。病棟に配置する臨床専任薬剤師の数も、2年前の3名から現在では16名へと増員された。
薬剤部における業務内容の拡充という中で、医薬品に関する最新情報の収集、医師や看護師への分かりやすい伝達といった院内サービスが、医薬品情報統合システムの導入によって向上、効率化される意義は大きかったという。後発品など医薬品にかかわる資料作成にも活用。「JUS.D.Iで情報を選別し、 CSV形式でダウンロード、それを加工して短時間に資料を作成できる。臨床業務に近いサービスへ、より力を傾けることができる」と木村氏は述べる。
薬剤名が多少あいまいでも、検索時の高いヒット率
入院患者の持参薬については、2007年12月以降、病棟担当薬剤師を中心に薬剤部が全面的に関与し、薬剤の鑑別、適正な使用法に関する医師へ十分な情報提供を開始。服薬における安全性の確保をいっそう強化した。
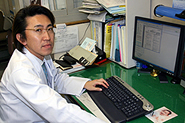 「識別コード入力による自己監査のプロセスを取り入れられたのは、正確を期する上で大きな前進につながった」と木村氏
「識別コード入力による自己監査のプロセスを取り入れられたのは、正確を期する上で大きな前進につながった」と木村氏
「ある程度の大病院であるため、院内採用薬はそれなりの規模で網羅しているが、それでもおおよそ、持参薬の3~4割が、当院では採用していない薬。未採用薬や同効薬についての情報をいかに素早く的確に入手するかが、臨床業務にも影響してくる」(木村氏)。ここでも、JUS.D.Iが果たす役割は大きい。
木村氏は次のように述べる。「JUS.D.Iは、検索の際のヒット率が非常に高い。紹介状や薬袋などに記載されている医薬品名が、持参薬と微妙に異なる場合も稀にあるが、そうした名称の多少のゆらぎがあっても、名称の類似する薬剤の候補がいくつか表示される。経過措置になったものもすべて検索対象に含まれているので鑑別効率は高い。同一薬剤でも少しずつ名称変更がなされるため、経過措置薬に関しても実物と画面と照らし合わせて確認でき正しい名称で報告できる。識別コード入力による自己監査のプロセスを取り入れられたのは、正確を期する上で大きな前進につながった」。
各専門領域の相乗効果により、医療の質を高めていく
今後もさらに薬剤部では、院内への情報提供サービスの品質を高めていくために、より質の高い『医薬品情報検索システム』の整備を目指していくという。
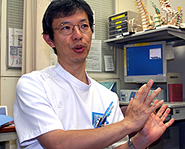 「信頼で結ばれた各領域のチームプレーによって全体の質を相乗的に高めていく。それがこれからの医療のありようだ」と加藤氏
「信頼で結ばれた各領域のチームプレーによって全体の質を相乗的に高めていく。それがこれからの医療のありようだ」と加藤氏
木村氏は次のように話す。「医療の現場で医薬品を取り扱う上では添付文書が基本。それはJUS D.I.でできる。しかし、添付文書に記載された情報を超えた症例はたくさんある。そこで日々の治療で蓄えた知見をデータベースなどに集約し、最善の治療を施したい。院外機関が提供する、臨床に即した汎用性の高いデータベースにも注目している。それらを統合した当院独自の情報基盤の整備は、いわゆる EBM(Evidence Based Medicine)に通じる」。
麻酔科の加藤氏は、個人情報保護などのセキュリティ上のハードルがあることは重々承知と断った上で、「医薬品情報統合システムと、電子カルテの親和性向上によって、もっと業務を効率化できるはず」と期待を寄せる。「電子カルテ全般についても、同じ病名の患者情報を横断的に分析できれば、新たな治療上の発見があるかもしれない。いまは各社によってカルテの仕様も大きく違う。医療機関の連携を踏まえた電子カルテの有効活用のためにも、安全性と利便性のジレンマをはじめ、各種の課題をそろそろ解決しなければならない」と述べる。
「薬については薬の専門家によく相談する。電子カルテなどの情報システムについてもその分野の専門家でなければ分からないことがある。そして医師に医師の役割がある。信頼で結ばれた各領域のチームプレーによって全体の質を相乗的に高めていく。それがこれからの医療のありようだ」(加藤氏)。

病院概要
- 名称:
- 東京女子医科大学病院
- 住所:
- 東京都新宿区河田町8-1
- Webサイト:
- http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/
- システム開発・導入:
- 日本ユースウェアシステム(東京・品川)
- 総販売元:
- スズケン
※このコンテンツは、
日経メディカルオンライン「医療とIT」に掲載(2008年3月14日)された記事から転載したものです。日経BP社に転載許可をいただいております。